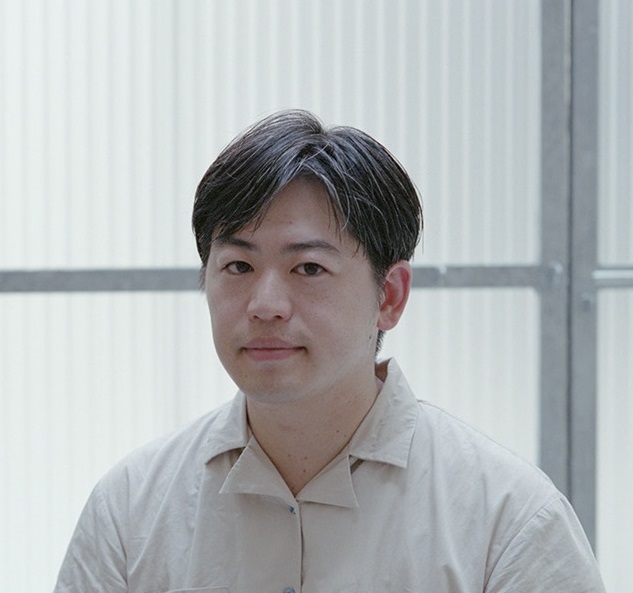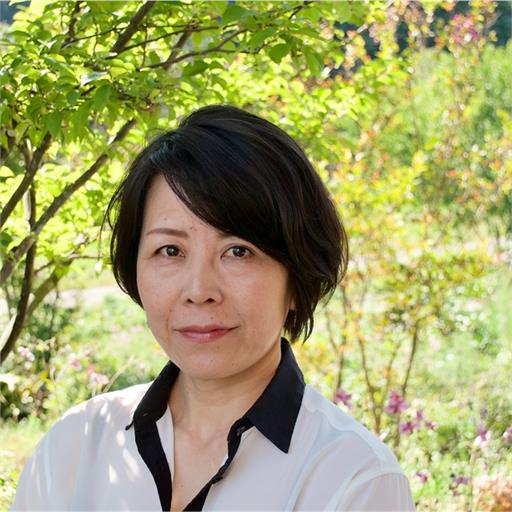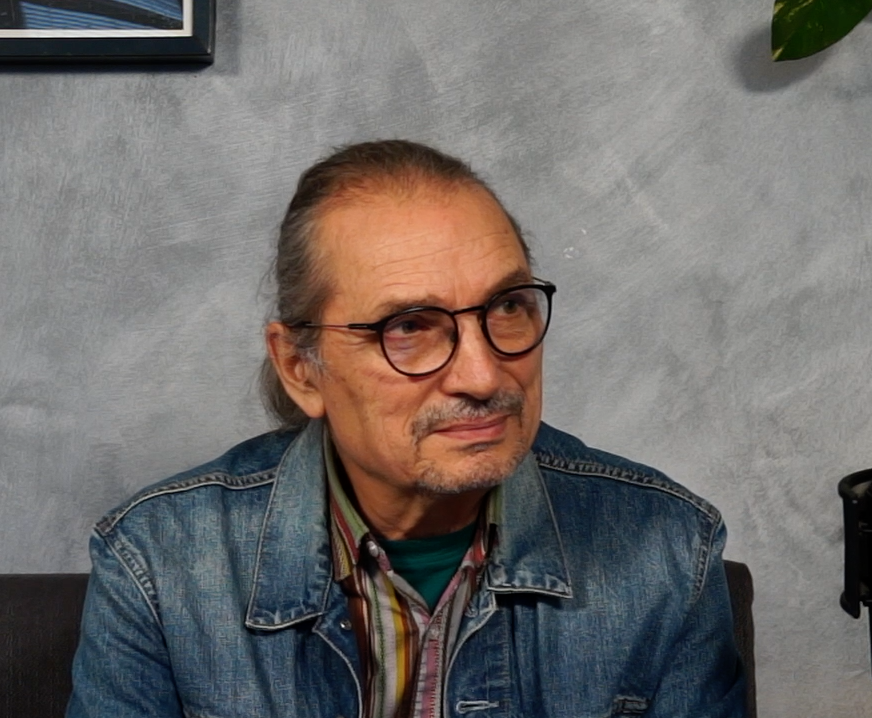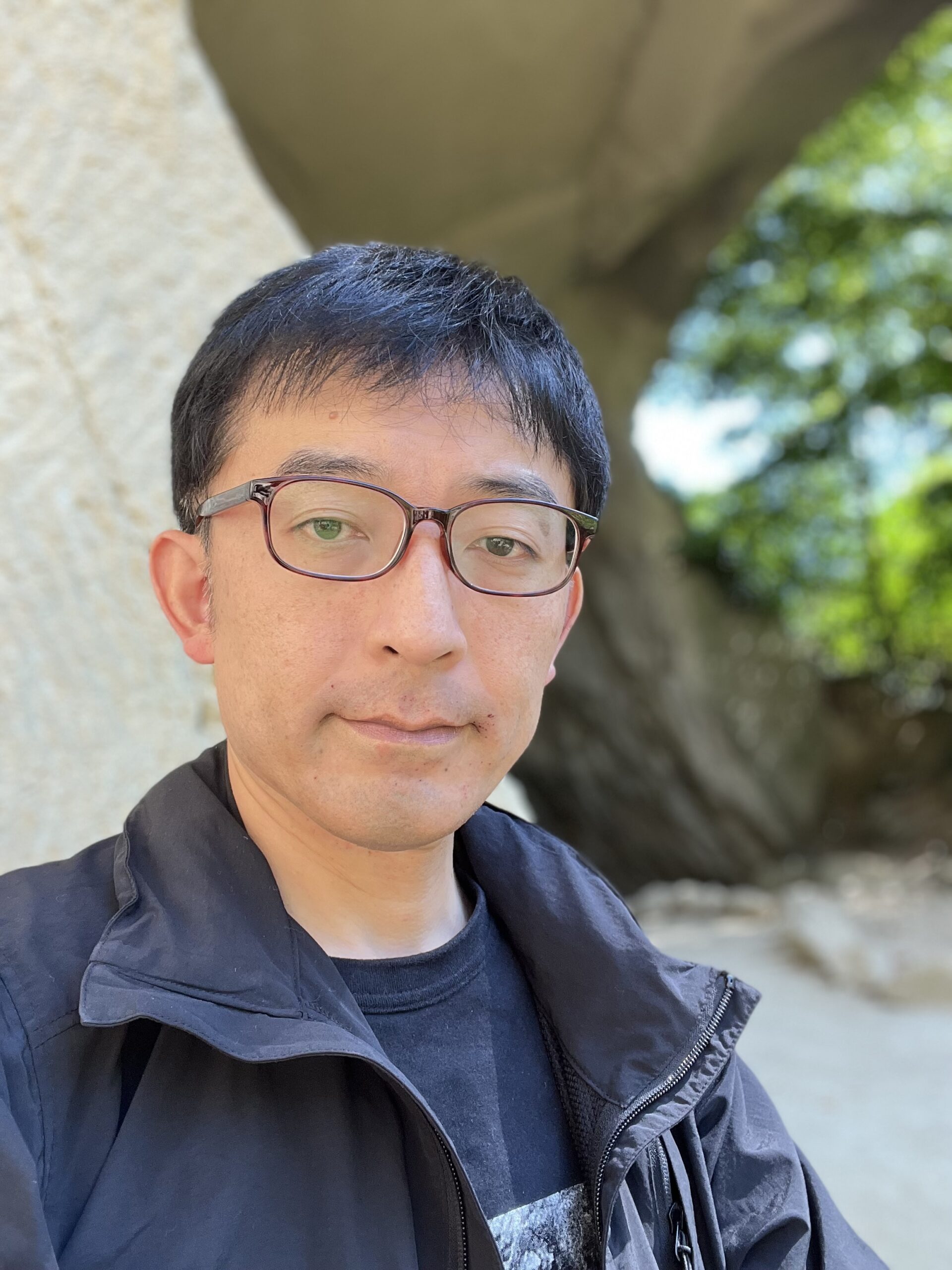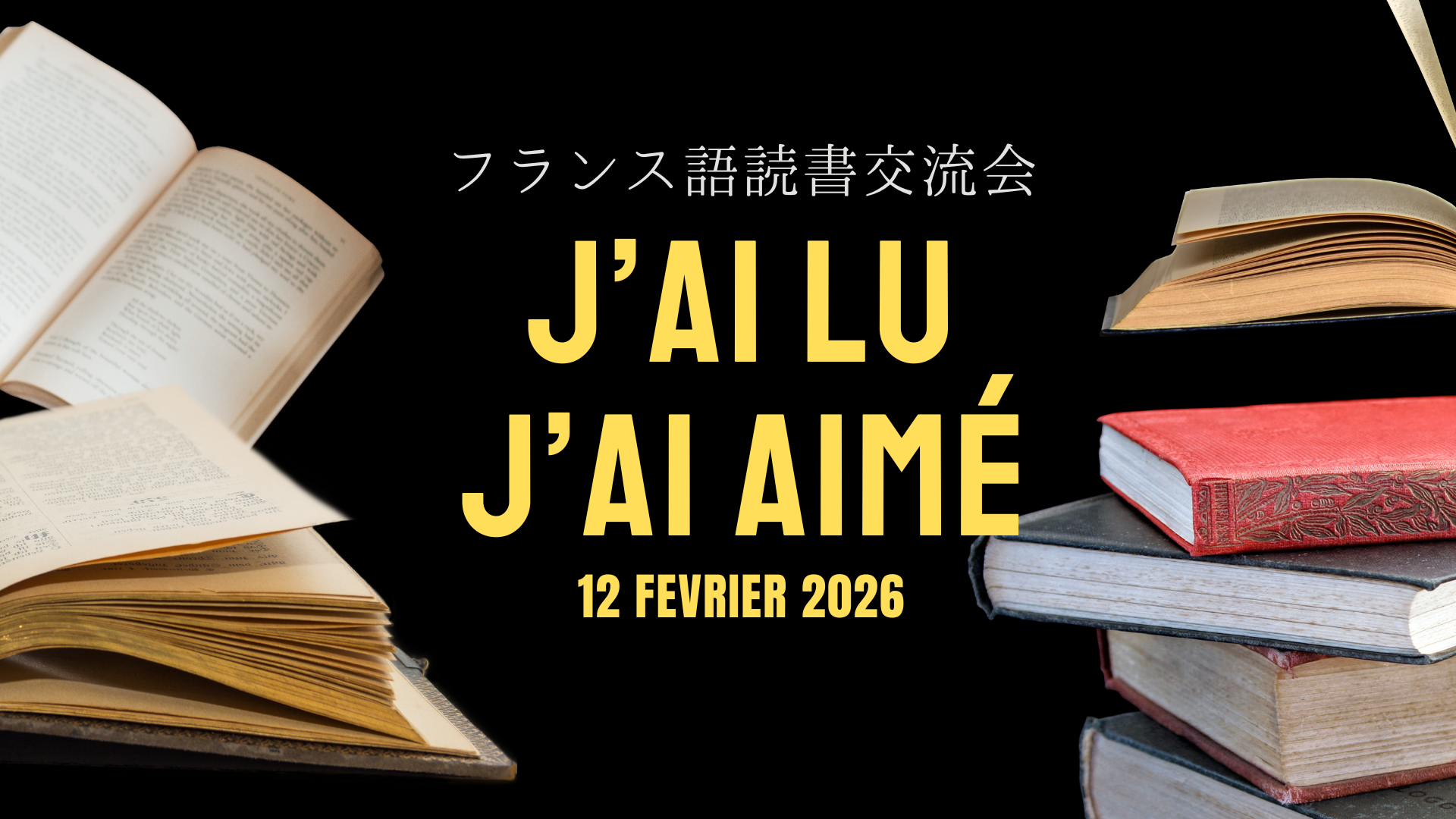千鹿頭 CHIKATO
(2023年/日本/40分/カラー/デジタル)
※日本語を解さない方もご覧いただけます
長野県諏訪地方での滞在調査を経て、同地の神話、信仰、民俗などから得たインスピレーションをもとに、性愛、捕食、屠殺、葬送といった生命の普遍的営為がもつ両義性を創作神話とした映像作品。タイトルは、狩猟神ともされる古代諏訪の「千⿅頭神」に由来するが、本作では、その地にかつていた神々や人々、あるいは森の総称としている。森の中で複数の物語が、相互に比喩的な関係を織りなしていく。
協力:対話と創造の森
© Jun Yamanobe