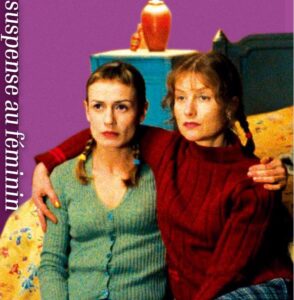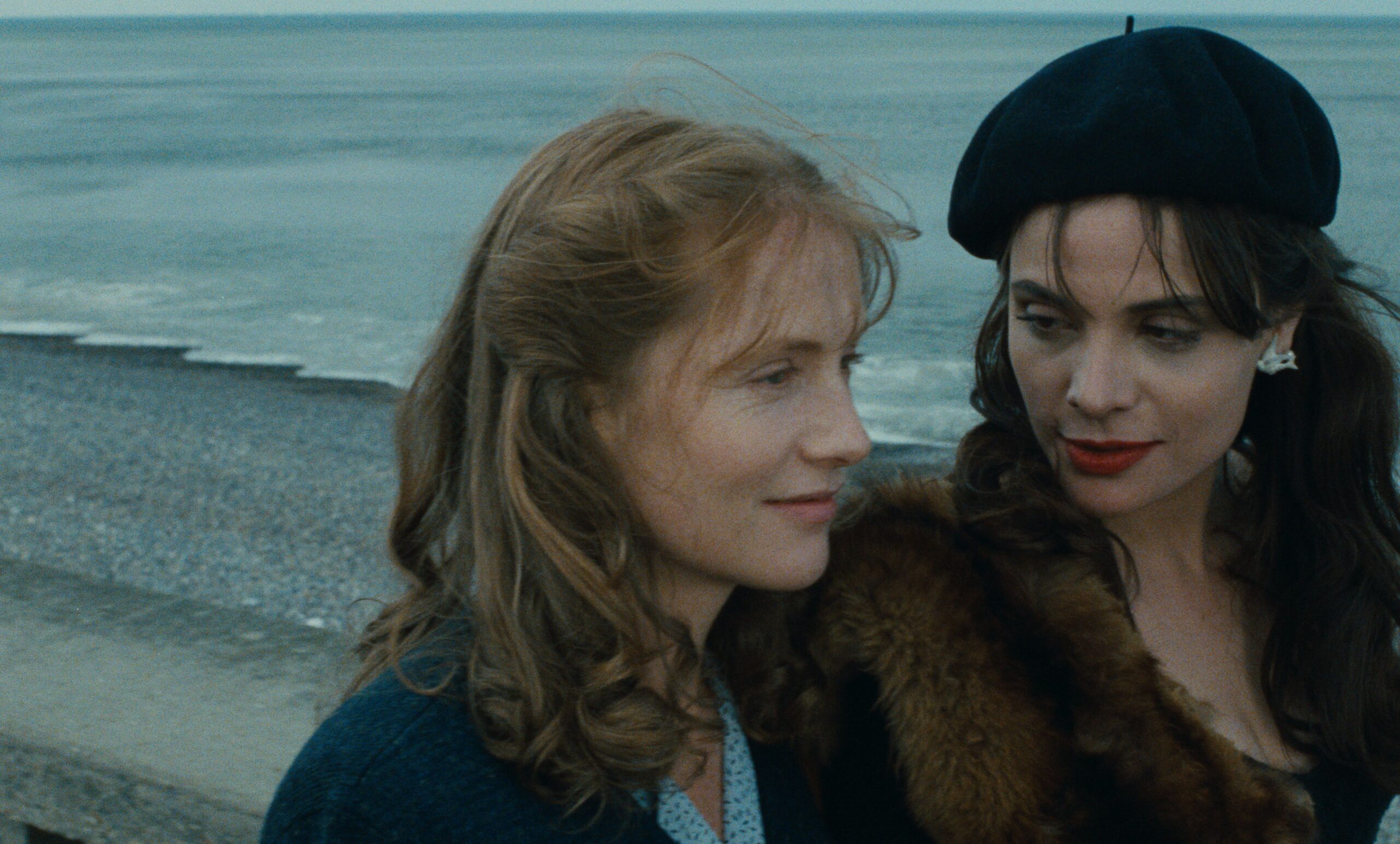イザベル・ユペール スペシャルトークショー

2025年10月13日、東京芸術劇場にて開催されたロバート・ウィルソン演出作品「Mary Said What She Said」の一人舞台の公演ために来日したイザベル・ユペールさんをお迎えし、『主婦マリーがしたこと』上映後に、トークショーを行いました。
タイトなスケジュールの中、短い時間ではありましたが、『主婦マリーがしたこと』について、そしてシャブロル監督と長年にわたりどのように協働し、女性の人物像に血肉を与えていったのか、力強く、明確な言葉でお話しいただきました。
以下に、この貴重なトークショーの採録を掲載させていただきます。
*こちらのイベントは、2025年10月3日(金)〜10月26日(日)、東京日仏学院にて開催された特集「戦後80年 日仏の交差する視点」の一環として行われました。
「人間性そのものを描き、偶像化せずに、そこから真実を浮かび上がらせるのが、シャブロル監督の巨匠たる所以です」
イザベル・ユペールとクロード・シャブロルの出会いは、1978年の『ヴィオレット・ノジエール』から2006年の『権力の陶酔』まで、7本の映画を生み出した。
7本の映画の中で、イザベル・ユペールが演じる女性のキャラクターは反復しながらも、変化していく。死刑判決を受けた女、毒殺する女から服毒する女へ、不満と憂鬱に苛まれ、別の場所を求める女性、殺人者、そして生き残り、駆け引きをし、自分の意志を貫く権力者としての女……。
ギロチンで処刑された最後の女性
司会:イザベルさんは1978年の『ヴィオレット・ノジエール』で初めてクロード・シャブロル監督の映画に出演され、その後、次々に傑作を共に生みだされていかれました。本日上映した2作目の『主婦マリーがしたこと』まで、最初の作品から10年の月日が流れていますが、それはどうしてだったのでしょうか?
イザベル・ユペール(以下ユペール):そうですね、とくにわたしの方ではこれといった理由はないのですが…。とにかくシャブロル監督と一緒に映画を撮りたいという気持ちはずっとありました。『主婦マリーがしたこと』以降、仰られたように、わたしは定期的にシャブロル監督と仕事を重ね、彼が亡くなる直前まで共に仕事をしました。『主婦マリーがしたこと』は、実はわたしが見つけてきたテーマなんです。ちょうど当時、その実話に基づいた本が出て、それをシャブロル監督に話したところ、とても興味を持ってくれました。そこで書かれていた歴史は、フランスの歴史のなかでも特別な歴史です。みなさんが今ご覧になった女性は、(フランスの歴史上)ギロチンで処刑された最後の女性です。ほんとうに暗い歴史でした。
司会:『主婦マリーがしたこと』は、今回、戦後80年をテーマとする特集の中で上映させていただき、この特集ではマルセル・オフュルスの『悲しみと哀れみ』という作品も日本初上映されています。まさにこの映画と同じ、占領下の話、しかも女性の立場から描かれている作品をイザベルさんが見つけてこられたというのは、素晴らしいですね。クロード・シャブロルの映画で描かれる人々は、悲しいとか、この人は悪い人だとか、そういうカテゴライズがまったくなく、最初は普通の人として描かれていて、だんだん日常のシチュエーションから、その人の中にあるいろいろなものが見えてくると思うんです。この映画もごくありきたりなシーンから始まりますよね。
ユペール:そうなんです。マリーはヒロインとして登場してきませんし、普通の人で、どちらかというとあまり感じがよくない、だからこそ愛おしいところがあります。浮気もしますし――浮気をするから感じが悪いってわけではまったくありませんけれど。とにかく彼女には道徳感の意識があまりないんです。子供はとても好きですが。極限の生活のなかで、なんとか生き延びていこうという本能がある人です。おそらく、フェミニズムという言葉がなかった時代に、意識せずそのパイオニアといえるような存在だったのではないでしょうか。困っている女性を助けたい、そして自分自身もその状況を切り抜けたというところがありました。でも彼女のなかには、政治的なイデオロギーや、国家を侮蔑しているという意識は、まったくありません。ただ、結局のところ、最後のギロチンで処刑された女性の一人となったことによって、ドラマのなかで、アンチヒロインとして、後世に残った人です。
司会:マリーの周りにどんどん女性が集まってきますよね。いまイザベルさんがおっしゃったように、知らぬ間に彼女は女性たちを助けています。隣人のマリー・ピネルさんや、娼婦のマリー・トランティニャンだったり、ドミニク・ブランだったり。それから、牢屋に入っても、ダニーという囚人の友達ができたり、そういった、女性たちの星座ができてくる。この女性たち、女優さんたちとの、コラボレーション――コラボレーションという言葉はこの時代の映画について使うべきではないでしょうが――、こうした仲間たち、キャスティングというのは、シャブロル監督がお決めになったんでしょうか。それとも、イザベルさんといっしょに決めていったんでしょうか。
ユペール:キャスティングは100%シャブロル監督です。実はマリーの娘モーシュ、小さいときではなく、4歳くらいになった女の子は、わたしの娘のロリータ・シャマが演じています。なので、わたしも多少は関わったと言えるかもしれませんね。女優さんの名前をたくさんあげていただきましたが、マリーの夫のポール役を演じているフランソワ・クリュゼもすばらしいですよね。彼は妻に見放された夫を演じているわけですが、そうした人間のいいところと欠点を、人間目線で描いているところが、シャブロルのすごいところだと思います。ヒーローのような存在はいません。上でもなく下でもなく、人間性そのものを描き、人間を偶像化せずに、そこから真実を浮かび上がらせるのが、シャブロル監督の巨匠たる所以だと思います。
歌う女
司会:この映画でイザベルさんは歌ってらっしゃいますよね。実は、ここのホールで、数週間前に、『アロイーズ』という、リリアン・ド・ケルマデックの作品を日本で初めて上映して、そこでもイザベルさんは歌っていらっしゃいました。歌うマリーの像は、原作にあったのか、それともイザベルさんの希望だったのか教えてください。
ユペール:シナリオにはマリーが歌うことは書かれていましたが、原作というか、インスピレーションのもとになった本は小説的なものではなくて、忘れられた、あのマリーのモデルになった女性を世に残すための、史実的な本だったんです。そこからシャブロルは、マリーという人物を、映画的な人物として造形していきました。思い返せば、わたしは、映画の中で歌ってみたいと提案し、ちょっとしたアイデアを彼に吹き込んだかもしれません。そうすると、シャブロルは、難しい人ではないので、「歌いたいのか、じゃあ歌ったらいいよ」と提案を受け入れてくれました。結果的にすごくいいアイデアだったなと思います。なぜなら、マリーが、アーティストとして、自分はこうなりたいという夢をあの境遇で抱くのは、彼女をとても魅力的な、感動させるような人物にさせているから。
司会:本当ですね。シャブロルさんとの共同作業はとてもシンプルだと仰られました。『沈黙の女/ロウフィールド館の惨劇』の撮影現場のメイキング映像を拝見したのですが、とても楽しそうでした。シャブロル監督と、イザベルさんと、サンドリーヌ・ボレーヌさんが、すごく楽しそうに撮っているなという感じがしました。そうやって、イザベルさんたちの提案も受け入れるし、ちょっとしたことでアイデアを出し合ったりしながら撮っているなという感じがしたのですが、例えば、動き、シャブロル監督の映画って、家とか建築がすごく大事な映画だと思うんですけど、そのなかでの動きというのは、シャブロルはかなり指示を出していたのか、それともイザベルさんたちが自由にされていたのかを教えてください。
ユペール:シャブロルは、俳優に指示をほとんど与えない監督でした。『主婦マリーがしたこと』にかんしては、一度だって指示をもらったことはありませんでした。ただ映画というものは、自律的なカメラがあって、照明があって、演出があって、そして台詞があって、といった装置ができていれば、わたしたち俳優は、そこにすうっと浸透していくような形で入っていくもので、なにかこうしろ、ああしろといった指示は必要ありません。シャブロル自身も、俳優たちは完璧に知らないけれども、知らないなりに演技をしていく、俳優に好きにやらせて、それを捉えようとするのが好きな監督でした。
司会:イザベルさんがメイキングのなかで、クロード・シャブロルの映画に出るということは、蝶に網にかかっているのを、昆虫学者が眺めているかのようで、その網とはカメラであり、でも、その網のなかでは本当に自由に動けるのだ、と仰っていましたが、今でもそんなふうに覚えていらっしゃいますか?
ユペール:その話をしたことはよく覚えています。(シャブロルの映画は)演出というものがすごく決まっていて、まるで俳優たちは囚われの身であるような気がするかもしれませんが、その制約があるからこそ、すごく大きな自由を得られます。わたしたち俳優が、すこし陽気であったり、悲しかったりしたとしても、そういうことは取るにとらないくらい、彼の演出には、力強く強烈なものがあります。シャブロルは強烈な視点を持っていて、だからこそわたしたち俳優は、そのなかで自由に演技をすることができるのです。
ヒューマニスト、クロード・シャブロル
司会:クロード・シャブロルがすごくフェミニストだと言う人はあまりいないかもしれない。でも、シャブロル監督とイザベル・ユペールさんの映画を見ていると、女性が核として描かれていて、そのなかでイザベルさんが演じられている女性が、少しずつ時とともにどんどん変わっていくのを発見します。シャブロル監督が、ユペールさんとずっと撮影していくうちに、世界がどんどん女性化している、その世界をユペールさんとともに映画のなかで表現できているということをお話になっていましたが、クロード・シャブロルはフェミニストでしょうか。
ユペール:シャブロル監督は、わたしから見るとフェミニストという定義には収まらず、ヒューマニストと呼ぶほうが近いように思えます。ヒューマニストのなかにフェミニストもはいっていれば、あるいは、他の社会的なヴィジョンも盛り込まれると言うほうがいいでしょう。たしかに、女性に大きな居場所を与えている作家ではあります。わたしと一緒に仕事をした作品のなかでは、確かにそうでした。ただ彼は、両義性、曖昧さ、矛盾のマエストロでもあるわけです。彼がステファーヌ・オードランといっしょに作品を撮っていた時代も、とても素晴らしい作品が多いです。そうですね、こう言っていいのなら、わたしは彼が語ろうとしているストーリーのなかの真実に関して、できるだけ的確に、志高く臨もうとしていました。そこからおのずと、物語のなかの倫理というか、道徳というものが、できるだけ浮かび上がってくる。そういう巨匠じゃないかというふうに思っています。常に人物たちは、時代のなかに刻印されていて、あるいは政治的立場、歴史、社会的制約のなかで闘っています。『沈黙の女』について、シャブロル監督は「これはマルクス主義の映画であると言っていました。たしかに彼にはマルクス主義的なところもあるかもしれません。
司会:ぜひ、シャブロル監督とイザベルさんの7本の映画の特集をしたいなと思いました。皆さま本日はありがとうございました。
司会:坂本安美
通訳:人見有羽子
採録:衛藤萌子
協力:ミモザフィルムズ
【関連企画】
クロード・シャブロル特集2026 女性形のサスペンス
会期:2026年1月16日(金)~2月1日(日)
会場:東京日仏学院エスパス・イマージュ
シャブロルが“女性を核に据えた”名作を厳選した7本を特別上映。極上の「女性形のサスペンス」の世界をじっくりとご堪能ください。
「シャブロルは善と悪というテーマに関心を持ち、人間の運命に悪の根源がどのように現れるかを生涯にわたって考察し続けました。(…)シャブロルはフェミニストであるとともに、それを超えて人間を深く洞察するヒューマニストといえるでしょう」イザベル・ユペール